業界規模:1.8兆円市場の停滞と構造変化
矢野経済研究所の調査によると、2024年の国内葬祭ビジネスの市場規模は、事業者売上高ベースで1兆8,300億円(前年比108.2%)と推計されています。これは、日本の高齢化に伴う年間死亡者数の増加が主な要因です。死亡者数は2040年頃にピークを迎えるまで増加が見込まれており、市場の需要自体は当面続くと考えられます。
しかし、市場規模の長期的な見通しは、横ばいから微増に留まると予測されています。その最大の要因が、葬儀一件あたりの単価の下落です。後述するように、葬儀の主流が大規模な一般葬から小規模な家族葬へとシフトしたことで、一葬儀あたりの売上が大きく減少しているのです。実際に、2032年の市場規模は1兆7,684億円と予測されており、コロナ禍以前の規模には及ばない可能性が示唆されています。
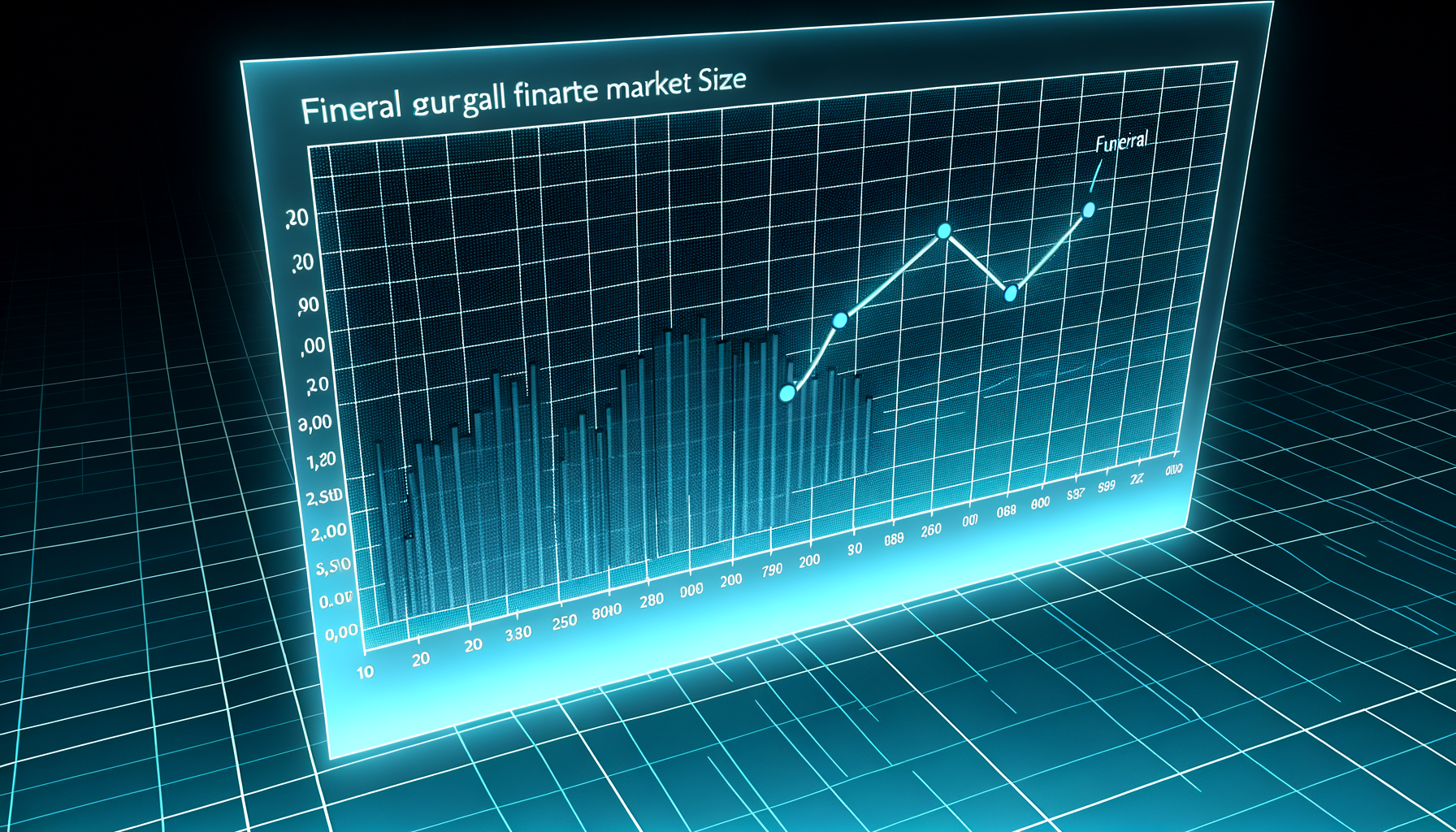
死亡者数は増加するものの、単価下落により市場規模は伸び悩む。
ビジネスの変遷:一般葬から家族葬へ
かつて日本の葬儀は、近隣住民や会社関係者なども広く招き、盛大に行われる「一般葬」が当たり前でした。これは、葬儀が故人のためだけでなく、遺された家族が地域社会との関係性を確認し、維持するための重要な社会的機能も担っていたためです。
しかし、1990年代以降、核家族化や都市部への人口集中が進み、地域コミュニティとの繋がりは希薄化していきます。同時に、経済的な価値観の変化や、個人の意思を尊重する風潮の高まりも相まって、葬儀に対する考え方も大きく変化しました。
こうした社会背景の中で、2000年代から徐々に広がりを見せたのが、家族や親族、ごく親しい友人といった、本当に近しい人々だけで故人を見送る「家族葬」というスタイルです。さらに、通夜や告別式といった儀式を省略し、火葬のみを行う「直葬(火葬式)」を選ぶ人も増加しました。
この小規模化・簡素化の流れは、2020年以降の新型コロナウイルスのパンデミックを経験したことで一気に加速し、現在では家族葬が葬儀形式の主流として完全に定着したと言えるでしょう。この変化は、葬儀社のビジネスモデルにも大きな影響を与え、価格の透明性や、より個別化されたサービスの提供が求められる時代へと移行しています。