定着した「家族葬」と単価の下落
現在、日本の葬儀形式の主流は、間違いなく「家族葬」です。鎌倉新書が2024年3月に実施した調査では、施行された葬儀の半数以上が家族葬であったことが示されています。この背景には、費用を抑えたいという経済的な理由だけでなく、「故人とゆっくりお別れの時間を過ごしたい」「形式的な弔問客への対応は避けたい」といった、遺族の精神的なニーズの変化があります。
この家族葬の普及は、葬儀一件あたりの単価の下落に直結しています。参列者が少ないため、飲食費や返礼品費が減少し、会場も小規模なもので済むためです。同調査によると、葬儀費用の全国平均総額は約118.5万円ですが、これはあくまで平均値です。葬儀の規模が大きくなるほど費用は高額になり、一般葬、家族葬、一日葬、直葬の順に安価になる傾向が明確に見られます。
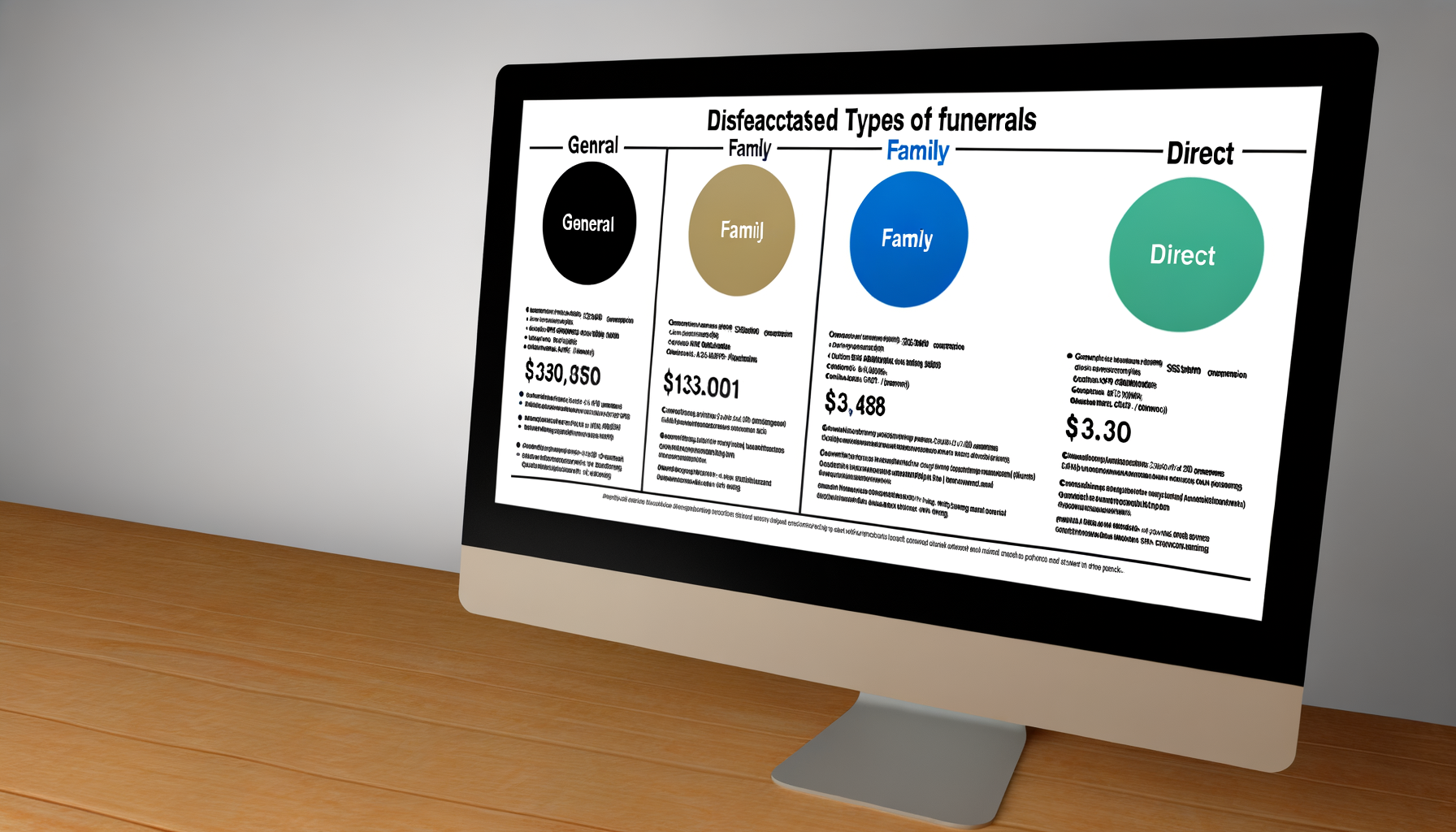
葬儀の小規模化は、費用の低下と直結している。
アフターコロナで見られる「一般葬」への回帰
一方で、興味深い動きも見られます。家族葬の割合は、前回調査と比較すると実は減少しており、代わりに一般葬の割合が増加しているのです。これは、新型コロナウイルスの5類移行に伴う行動制限の緩和が大きく影響していると考えられます。
パンデミック中は、感染対策のために半ば強制的に小規模な葬儀しか選べない状況でした。しかし、その制約がなくなった今、「故人と生前お世話になった方々にも、きちんとお別れの場を設けたい」と考える遺族が一定数いることがうかがえます。これは、葬儀の形式が「小規模化一辺倒」ではなく、故人や遺族の意向によって多様な選択がなされる時代に入ったことを示唆しています。
求められるニーズの多様化への対応
現代の葬儀社には、こうした消費者の多様なニーズに柔軟に応える姿勢が求められています。画一的なプランを提示するのではなく、顧客一人ひとりの事情や想いを丁寧にヒアリングし、最適な形を提案するコンサルティング能力が不可欠です。
- 費用を抑えたい層には、明朗会計な小規模プランを。
- 伝統的なお見送りを望む層には、格式ある一般葬を。
- 故人らしさを表現したい層には、音楽葬や無宗教葬といった自由な形式を。
このように、様々な選択肢を用意し、それぞれのメリット・デメリットを正確に伝えることができる葬儀社こそが、今後、顧客からの信頼を勝ち得ていくことになるでしょう。